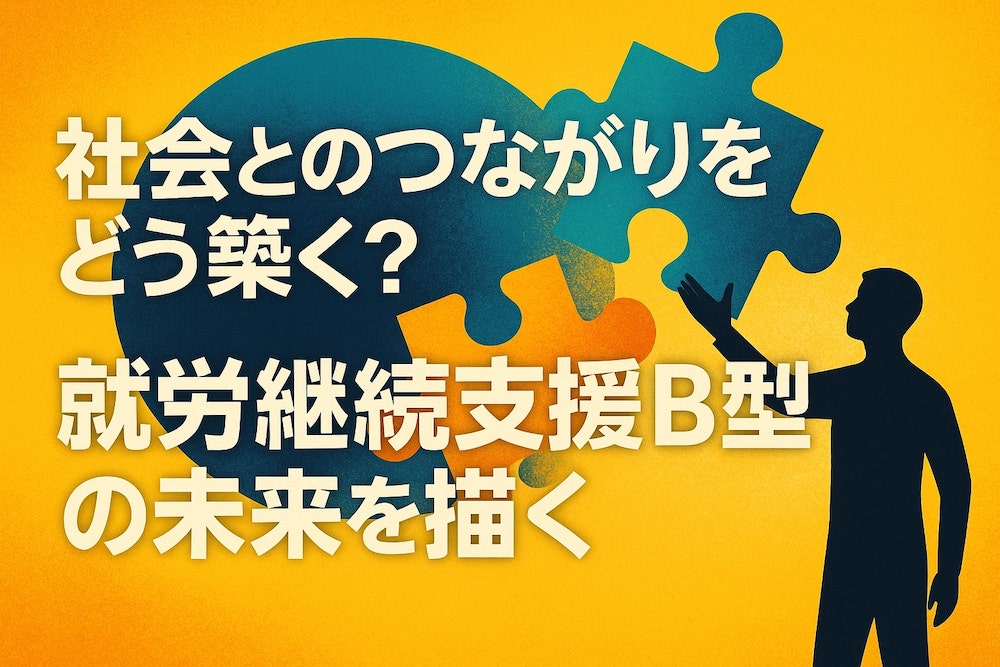最終更新日 2025年10月11日 by daisyw
就労継続支援B型とは、一般企業での就労が困難な障害のある方に対して、働く場と機会を提供する福祉サービスである。
雇用契約を結ばず、一人ひとりの状態に合わせた柔軟な働き方が可能なところが特徴だ。
厚生労働省の調査によれば、令和3年現在、全国で28万人以上の方がこのサービスを利用している。
私はこの就労継続支援B型の現場で、35年にわたり障害福祉の実践を重ねてきた。
東京での勤務を経て、地元の熊本県人吉市へUターンし、2005年にNPO法人「ひとひら」を立ち上げた経緯がある。
「ひとひら」の名前には、一人ひとりの小さな力が集まれば大きな力になるという思いを込めた。
いつも思うのは、就労継続支援B型の本質は「働く」ことだけにあるのではないということ。
そこには「社会とのつながり」という、もっと大切な価値があるのではないか。
この記事では、私が35年間の福祉実践の中で見てきた就労継続支援B型の現状と課題、そして「社会とのつながり」をどう設計していくかについて考えてみたい。
なんば、じょばんとご一緒に考えていきましょうな。
就労継続支援B型の現状と課題
制度の概要と設立の背景
就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つである。
一般企業等での雇用が困難な障害のある方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のための訓練を行うものだ。
この制度が本格的に始まったのは、2006年の障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)施行以降である。
それまでは「授産施設」や「小規模作業所」と呼ばれるものが各地にあり、障害のある方の日中活動の場となっていた。
しかし、施設によって支援の質や工賃に大きな差があったため、全国で一定の基準を設けた制度として就労継続支援B型が誕生したのだ。
現在では、令和4年時点で全国に15,748事業所が存在し、その数は平成27年から1.6倍に増加している。
B型事業所の特徴として、雇用契約を結ばないため労働関係法令の適用はなく、利用者は自分のペースで働ける点が挙げられる。
また、対象年齢に制限はなく、障害の種類や程度も問われないため、様々な状況の方が利用できる。
しかし、制度としては整備されたものの、実際の運営や支援のあり方には多くの課題が残されている。
現場で直面するリアルな課題
私がB型事業所の運営で最も難しいと感じるのは、多様な利用者ニーズへの対応だ。
ある利用者は「将来的に一般就労したい」と考え、スキルアップを求めている。
一方で「ここが居場所であればいい」という方もいれば、「少しでも工賃を上げたい」という方もいる。
これらの異なるニーズに一つの事業所で応えることは、正直言って容易ではない。
「この子は、ほんなこつでけん(こんなことができない)」と思われがちな利用者も、実は適切な環境と支援があれば能力を発揮できるものだ。
問題は利用者側ではなく、私たち支援者の想像力と工夫の不足にあるのかもしれない。
もう一つの課題は工賃の低さである。
全国平均の月額工賃は令和4年度で1万7,031円、時間額は243円にとどまっている。
最低賃金の適用がなく、生産活動の対価として支払われる工賃だけでは、経済的自立は難しい現実がある。
さらに、地域社会との接点が限られている事業所も多い。
地域から隔離された「福祉の島」になってしまっては、本来目指すべき社会参加や包摂から遠ざかってしまう。
利用者が社会とつながる回路をどうやって作るか、これは私たちB型事業所の永遠のテーマでもある。
利用者・家族・支援者の視点から見る制度の限界
現行の就労継続支援B型の制度には、それぞれの立場から見た限界がある。
利用者の視点からは「工賃が低すぎる」「やりたい仕事が選べない」という不満がよく聞かれる。
特に障害基礎年金だけでは生活が厳しい中、工賃の低さは深刻な問題だ。
家族の視点からは「将来の自立が見えない」という不安が大きい。
親亡き後、障害のある子どもが地域で暮らし続けられるのか、その見通しが持てないのだ。
また、就労継続支援B型を利用しながらも、送迎や生活面のケアを家族が担うケースも多く、家族の負担は小さくない。
支援者の視点からは、限られた報酬の中でサービスの質を維持する難しさがある。
令和6年度の報酬改定では工賃の低い事業所は報酬が下がる傾向にあり、経営的な圧迫を感じている事業所も少なくない。
また、支援の専門性を高める研修機会や人材確保も課題となっている。
このような制度の限界を知りつつも、私たちはその枠内で最大限の支援を模索している。
制度を批判するだけでなく、その隙間を埋めるような実践が求められているのだ。
利用者一人ひとりの暮らしと人生を見つめながら、本当に必要な支援とは何かを問い続けることが大切だと思う。
「社会とのつながり」をどう設計するか
つながりの形:経済、関係性、承認
社会とのつながりは様々な形で存在する。
最も基本的なのは「経済的なつながり」であり、これは工賃という形で表れる。
しかし、工賃の向上だけが目標ではない。
私が大切にしているのは「関係性のつながり」だ。
事業所の中だけでなく、地域の人々との交流を通じて生まれる人間関係は、利用者にとって大きな財産となる。
「こんにちは」と挨拶を交わす関係、顔と名前が一致する関係が増えていくことで、地域での居場所が広がっていく。
さらに重要なのが「承認のつながり」である。
自分の仕事や存在が誰かに必要とされ、感謝されることは何物にも代えがたい。
「あんたのおかげで助かった」という一言が、その人の尊厳と自信を支える。
これらのつながりをバランスよく育むことが、就労継続支援B型の本質的な役割ではないだろうか。
経済的な自立だけを目指すのではなく、人としての尊厳と社会参加を実現する多様なつながりを設計することが重要だ。
人吉の方言で言えば「つながりのあつか(温かさ)」を大切にしたいものだ。
地域社会との接点を生む実践例
全国各地で興味深い実践が生まれている。
例えば、地域の高齢者宅の庭掃除や買い物支援を行うB型事業所は、地域に必要とされる存在として認知されている。
利用者は「ありがとう」と直接言われることで、自分の仕事の意味を実感できるのだ。
また、地域の農家と連携し、農作業の一部を請け負う取り組みも広がりつつある。
繁忙期の人手不足解消に貢献しながら、季節の流れを体感できる農作業は、利用者にとっても充実感がある。
「農福連携」と呼ばれるこの取り組みは、今後さらに発展が期待される分野だ。
このような地域密着型の取り組みは、東京都小金井市を拠点とするあん福祉会の評判と地域に根ざした実践からも学ぶことが多い。
精神障害に特化した支援を30年以上続け、地域コミュニティとの強い絆を築いている事例は参考になるだろう。
さらに注目したいのは、地域の飲食店やカフェを運営するB型事業所だ。
接客を通じて地域住民と直接交流できるだけでなく、食という普遍的な価値を通じたつながりが生まれる。
「あの店のコーヒーは美味しい」と評価されることは、利用者の自信と誇りにつながる。
私たち「ひとひら」では、地元の祭りやイベントに積極的に出店している。
利用者が作ったパンや菓子を販売するだけでなく、準備から片付けまでを含めた地域行事への参加によって、地域の一員としての自覚が育まれる。
「ひとよしの祭りは、わったちゃ(私たち)がおらんと始まらん」と冗談交じりに言う利用者の表情は誇らしい。
「居場所」としてのB型事業所の可能性
就労継続支援B型の役割を考えるとき、「居場所」としての機能は見逃せない。
多くの利用者にとって、B型事業所は単なる「働く場」ではなく「安心できる居場所」でもあるのだ。
特に精神障害や発達障害のある方にとって、無理なく過ごせる場所の存在は大きい。
ある利用者は「家と病院以外に行く場所がなかった」と言う。
社会から孤立しがちな障害のある方にとって、毎日通える場所があるということは、生活リズムの維持につながる。
また、同じ悩みを持つ仲間との出会いは、孤独感の軽減にもつながっている。
居場所としての機能を重視するあまり、「甘え」や「ぬるま湯」になってはいけないという批判もある。
しかし、安心できる場所があってこそ、次のステップに進む力が湧いてくるのではないだろうか。
「居場所」と「就労の場」は対立するものではなく、両立させるべきものだと考えている。
B型事業所が目指すべきは、利用者一人ひとりの状態に合わせた「居場所」と「成長の場」のバランスではないか。
「今日も行きたい」と思える場所であり、同時に「明日はもう少し頑張ってみよう」と思える場所でもある。
そんな二面性を持った場づくりが、私たちの挑戦である。
未来に向けた実践と挑戦
「ひとひら」の取り組み:利用者主体の仕事づくり
私たちNPO法人「ひとひら」では、利用者が主体的に参加できる仕事づくりを心がけている。
「何ができないか」ではなく「何ができるか」に着目し、一人ひとりの強みを活かした作業設計を行っている。
これは「ストレングス視点」と呼ばれるアプローチで、障害福祉の基本的な考え方だ。
具体的な取り組みとして、利用者の声から生まれた「からいもパン」の製造がある。
人吉地域の特産品であるサツマイモ(からいも)をパン生地に練り込み、地元ならではの味を作り出した。
企画から試作、製造、販売まで利用者が関わることで、「自分たちのパン」という意識が生まれている。
また、地域の高齢者の話を聞き取り、昔の遊びや料理を記録する「聞き書き」プロジェクトも行っている。
障害のある利用者がインタビュアーとなり、地域の歴史を残す貴重な役割を担っているのだ。
このプロジェクトは利用者と地域の高齢者、双方にとって意義のある取り組みとなっている。
さらに、ICTを活用した在宅での作業にも挑戦している。
身体的な理由で通所が難しい方や、対人関係に困難を感じる方でも、自宅でデータ入力やWEB制作などの仕事に取り組めるようになった。
このように、多様な働き方の選択肢を増やすことも、私たちの重要な役割だと考えている。
熊本・人吉発の地域密着モデル
人吉市は人口約3万人の小さな町だが、だからこそできる取り組みがある。
顔の見える関係性の中で、障害のある方の理解と支援の輪を広げていけるのだ。
「ふるさとでいごっか暮らす(ふるさとで良い生活を送る)」という願いを実現するため、地域ぐるみの支援体制を築いてきた。
地域の農家との連携は、人吉ならではの取り組みだ。
球磨川流域の豊かな農地を活かし、無農薬野菜の栽培や山菜採りなど、都市部では難しい活動が可能になっている。
収穫した作物は地元の飲食店に納入することで、地産地消の流れを作り出している。
また、豪雨災害からの復興支援活動を通じて、障害のある方も「支援される側」から「支援する側」へと立場を変えることができた。
被災した高齢者宅の片付けや炊き出しの手伝いなど、できることで地域に貢献する経験は大きな自信につながる。
「困ったときはお互いさま」という相互扶助の精神が、障害の有無を超えたつながりを生み出している。
人吉の文化や伝統を活かした商品開発も進めている。
例えば、球磨焼酎の酒粕を使ったお菓子や、人吉の伝統工芸である球磨手漉き和紙を活用した商品など、地域の特色を前面に出した取り組みだ。
商品には必ず製作者の名前を入れ、作り手の顔が見える関係性を大切にしている。
このような地域密着型の取り組みは、全国一律のモデルではなく、各地域の特性を活かした展開が可能だ。
「人吉だからできること」を大切にしながら、他の地域でも応用できるエッセンスを見出していきたい。
小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらすと信じている。
「働く喜び」の再定義に向けて
就労継続支援B型を考えるとき、「働く」ということの意味を問い直す必要がある。
従来の「賃金を得るため」「生計を立てるため」という経済的価値だけでなく、もっと多様な「働く意味」があるのではないか。
私たちは「働く喜び」を再定義する試みを続けている。
例えば、「誰かの役に立つ喜び」がある。
自分の仕事が誰かの生活を支え、笑顔につながることを実感できれば、たとえ工賃が低くても大きなやりがいになる。
それは「ありがとう」という言葉に表れる、かけがえのない価値だ。
また、「成長する喜び」もある。
昨日よりも上手になった、新しいことができるようになったという実感は、人間の本質的な喜びである。
小さな成功体験の積み重ねが、自己効力感を高めていく。
さらに、「つながる喜び」も重要だ。
同じ職場の仲間との連帯感、地域の人々との交流など、仕事を通じて広がる人間関係は大きな財産となる。
「一人じゃない」という安心感が、明日への活力となる。
私たちは利用者と共に、こうした多様な「働く喜び」を日々の実践の中で見つけ出し、大切にしている。
経済的価値に還元できない「働く意味」に光を当てることで、就労継続支援B型の新たな可能性が見えてくるのではないか。
その先に、障害の有無を超えた「共に働く社会」の姿が浮かび上がってくると信じている。
制度と現場の橋渡し
支援者として感じる制度の盲点
35年間、障害福祉の現場で働いてきた経験から感じる制度の盲点がいくつかある。
最も大きいのは、「成果主義的な評価」が強まっていることだ。
平均工賃や一般就労への移行率など、数値化できる成果が重視されがちだが、それでは見えないものがある。
例えば、利用者の笑顔が増えたこと、自己肯定感が高まったことなど、数値では測れない変化は評価されにくい。
また、障害の重い方ほど「成果」が見えにくく、支援の必要性が高いにもかかわらず、報酬が低くなる矛盾もある。
こうした盲点が、現場の疲弊や支援の質の低下につながる危険性を感じている。
もう一つの盲点は、「制度の縦割り」である。
福祉、医療、教育、就労など、それぞれの制度が分断されていることで、一人の人間の人生を総合的に支える視点が失われがちだ。
例えば、B型事業所を利用しながら通院や生活支援も必要な方には、複数の制度を横断した支援が求められる。
さらに、地域差という盲点もある。
都市部と地方では、社会資源や移動手段、就労機会に大きな差がある。
全国一律の制度では、地域の実情に合った柔軟な支援が難しい場合がある。
こうした盲点を埋めるのは、現場の創意工夫と熱意だろう。
制度の限界を知りつつも、その中で最大限のサービスを提供する努力を、日々続けている。
「ぬくともなか(温かくない)制度に、あつか(温かい)実践を吹き込む」ことが、私たち支援者の使命だと思う。
政策提言と行政との対話のあり方
より良い障害福祉サービスを実現するためには、現場の声を政策に反映させる努力が欠かせない。
私は地域の障害福祉事業者団体の役員として、行政との対話の場を大切にしてきた。
時には厳しい意見をぶつけることもあるが、建設的な議論を心がけている。
効果的な政策提言のためには、具体的なデータと生の声の両方が必要だ。
「工賃が低い」と訴えるだけでなく、「なぜ工賃が上がらないのか」の分析と「どうすれば上がるのか」の提案を示すことが大切である。
そのために、日頃から事例や数字を丁寧に集め、整理しておくことを心がけている。
また、行政と対立するのではなく、共に考える姿勢も重要だ。
行政にも予算や人員の制約があり、すべての要望に応えられないことは理解できる。
しかし、限られた資源の中でより効果的な施策を実現するために、現場の知恵を提供することはできるはずだ。
全国の先進事例を学び、地域に合った形で応用する視点も大切にしている。
他県や他市の成功例を単に真似るのではなく、地域の特性や課題に合わせてアレンジすることで、実現可能な提案となる。
「よそはよそ、うちはうち」ではなく、良いものは積極的に取り入れる柔軟さが必要だ。
政策提言は一朝一夕に実を結ぶものではない。
地道な対話と実践の積み重ねが、少しずつ制度を変えていくのだ。
「石の上にも三年」ならぬ「提言の上にも三年」の忍耐を持ちながら、諦めずに声を上げ続けることが大切だと思う。
持続可能なB型のための仕組みづくり
就労継続支援B型が長期的に持続するためには、いくつかの仕組みが必要だと考えている。
まず、安定した仕事の確保が不可欠だ。
一時的なイベントや季節限定の作業だけでなく、通年で取り組める仕事を開拓することが重要である。
1. 官公需の活用
- 行政からの優先発注の仕組みを活用する
- 地域の公共施設の清掃や公園管理など、安定した仕事を獲得する
- 「障害者優先調達推進法」の活用を積極的に提案する
2. 企業との連携強化
- 地元企業の下請け作業を受注する関係を構築する
- 企業のCSR活動と連携した商品開発を行う
- 人材不足の企業に対して、B型から一般就労への流れを作る
職員の専門性向上も持続可能性の鍵となる。
情熱だけでは長く続かない。
福祉的視点と経営的視点を併せ持つ人材育成が必要だ。
また、利用者の高齢化への対応も課題である。
障害のある方も高齢化し、働き続けることが難しくなるケースが増えている。
就労継続支援B型と生活介護や介護保険サービスとの連携など、切れ目のないサポート体制の構築が求められる。
さらに、工賃向上のための計画的な取り組みも重要だ。
「高付加価値商品の開発」「作業効率の向上」「販路の拡大」など、総合的な戦略が必要となる。
特に「ブランディング」の視点は、近年重視されている。
持続可能な仕組みづくりには、利用者、家族、職員、地域、行政など多様な関係者の協力が不可欠だ。
一人の支援者が頑張るのではなく、チームとして取り組む体制を築くことが長続きのコツである。
「一人では遠くまで行けないが、みんなで行けば遠くまで行ける」という言葉を胸に、日々の実践を積み重ねている。
まとめ
現場から見える「つながり」の本質
35年間の現場経験から見えてきた「つながり」の本質は、その多様性にある。
経済的なつながり、関係性のつながり、承認のつながりなど、様々な形があり、それぞれが利用者の人生を豊かにする。
大切なのは、そのどれかだけを追求するのではなく、バランスを取りながら総合的に育んでいくことだろう。
就労継続支援B型は、単なる「福祉的就労の場」ではない。
それは地域社会の中で「つながり」を生み出す装置として機能する可能性を秘めている。
閉じられた空間ではなく、地域に開かれた場として発展していくことで、その可能性はさらに広がるはずだ。
現場で日々利用者と向き合う中で感じるのは、「つながり」は与えるものではなく、共に作り上げるものだということ。
支援する側とされる側という一方的な関係ではなく、相互に影響し合い、共に成長する関係性の中にこそ、真のつながりが生まれる。
それは時に言葉にならない微細な交流の中に宿るものだ。
福祉の未来に求められる姿勢と視点
これからの障害福祉には、どのような姿勢と視点が求められるだろうか。
まず、多様性を尊重する姿勢が不可欠だ。
一人ひとりの個性や希望に寄り添い、「正解は一つではない」という前提で支援を組み立てていく柔軟さが必要である。
また、「支援」を超えた「共生」の視点も重要だろう。
障害のある人を「支援の対象」としてのみ見るのではなく、地域社会の一員として、共に生きる仲間として捉える視点が求められる。
それは「支援する―される」という非対称な関係を超えた、対等な市民同士の関係性を目指すものだ。
さらに、社会変革の視点も欠かせない。
個別の支援を丁寧に行うと同時に、障壁のある社会の仕組みそのものを変えていく視点も持ち続けたい。
それは一朝一夕に実現するものではないが、小さな変化の積み重ねが大きな流れを作っていくと信じている。
これらの姿勢と視点を持ちながら、常に自らの実践を振り返り、学び続ける謙虚さも大切だ。
完璧な支援者などいない。
失敗や挫折を経験しながらも、「明日はもう少し良い支援ができるかもしれない」という希望を持ち続けることが、福祉の未来を切り拓く力になると思う。
一人ひとりが社会とどう関わるかを問い続ける
最後に、私たちが問い続けるべきは「一人ひとりが社会とどう関わるのか」ということだろう。
障害の有無にかかわらず、すべての人は社会の中で生きている。
その関わり方は十人十色であり、正解は一つではない。
就労継続支援B型は、その関わり方の一つの形だ。
経済的な自立だけが社会参加ではなく、様々な形での貢献や交流が、その人らしい社会との関わり方になりうる。
大切なのは選択肢の多様性と、本人の意思の尊重だろう。
私自身、35年間の福祉実践の中で多くの出会いに恵まれ、利用者から学ぶことが数えきれないほどあった。
彼らの人生の伴走者として歩む中で、「支援する側」の私も大きく成長させてもらった。
それは相互的な関係であり、一方通行の「支援」ではなかったと思う。
これからも「ひとひら」の活動を通じて、一人ひとりの可能性を信じ、社会とのつながりを育む実践を続けていきたい。
そこには紆余曲折があるだろうが、利用者と共に歩む過程そのものに価値がある。
「障害のある人もない人も、共に生きる社会」という理想を胸に、明日もまた現場に立ち続けたい。
熊本弁で言うなら「いっちょん、あきらめんでよかばい(少しも諦めなくていいんだよ)」という言葉を、利用者にも、共に働く仲間にも、そして自分自身にも贈りたい。
社会とのつながりを丁寧に紡ぎ続けることで、誰もが安心して自分らしく生きられる未来が少しずつ形作られていくと信じている。